

今月の絵『漆掻き鉋とレターパック』 by Ryu Itadani
民映研に教わる「関わりを分けずに見ることの大切さ」
9月といえば「敬老の日」。ステテコドットコムも素材づくりから、加工、縫製、仕上げなど、各産地でご年配の職人さんの経験と技術がなければ納得のいくものづくりには至りません。私たちの身近にもそんな「支え」がきっとたくさんあると思います。そこで今回は、私たちの暮らしがどのように年長者によって支えられてきたのかについて「民族文化映像研究所(以下、民映研)」代表の箒 有寛(ほうき ありひろ)さんにお話を聞いてみることにしました。
のっけから大失敗
――来たる9月の敬老の日にちなんで、私たちの文化の根底で年長者が果たしてきてくれた役割について教えていただきたいんです。参考にしたのがこの『民映研作品総覧』という資料なのですが……
箒さん まず「年長者」って分けたのが大失敗ですよ。
――え?
箒さん だって「暮らし」っていうのは赤ちゃんからお年寄りまで、みんなで生きてるところにあるわけですよね。それぞれの地域性や生き様があって。その中で年齢によってある程度役割が異なってくることは当然ですけど、でもそれは「年長者だから」って社会制度みたいに分けられた視点ではないんです。民映研の映画を見ていくとそれがよく分かりますよ。
――すみません、よく考えもせず「年長者」と一括りにしてしまっていました。
箒さん いえいえ。そこからお話をしましょうよ。

民族文化映像研究所 代表の箒有寛さん
民族文化映像研究所とは?
箒さん 民映研はもともと、民俗学者の宮本常一先生の弟子だった姫田忠義と伊藤碩男が、師の薫陶を受けて自分たちもその足跡を尋ね歩いていこうという思いが根底にあって、ある日、宮本先生に「姫田くんたちは映画を作る仕事もできるんだから、映像で残すことをやりなさいよ」って言われたことから始まったんです。1976年に正式に発足して、日本列島を中心に約120本のフィルム作品や教材用のVTRやテレビ番組などを作ってきました。
民映研の作品はほぼストーリーがなくて、ただその場を撮っている。それは宮本先生の教えでもあって、どこかの地域の神社のお祭りとか、部分ではなく、もっと全体、すべて、暮らし、場所をひっくるめて捉えることが民族学だってことをおっしゃってるんです。だから、主人公もほぼ出てこない。
――なるほど。では見る人によって視点はいろいろとあるわけですね。
箒さん そうです。だから(今回の話で言えば)どの映画を見てもそこに暮らす長老が知ってることを若者に受け継いでいくっていう順繰りがあるのは明快だし、農作業でも年上の者が教えている様子がいっぱい映ってるので「経験者が未経験者に教える」という場面は、すごくいっぱい出てくると思います。
――どこの土地にも蓄積された生きるための技術やノウハウを、若い世代が継承していく営みがあるんでしょうか。
箒さん その繰り返しなんです。私たちはそれを何千年もやってるっていうことです。
再現型ドキュメンタリー
箒さん もう1つ言うと、うちの場合はほぼ再現型ドキュメンタリーなんです。必ずしも事実だけを撮った社会派ドキュメンタリーではない。例えば名作と言われている『奥会津の木地師』という1976年に制作された「木地椀(木製のお椀)」を作る映画があるんですけど、木地師というのは漂泊の人たちです。定住者じゃないので僕らとはまた違う世界にいた人たちなんですけども、その木地師の暮らしを経験したことがある人に50年前の様子を再現してもらって撮ってるんです。
――再現というのはどういうことですか?
箒さん 木地師たちが小屋を建てることから始まるんですけど、3年ぐらいその周りの木を切ってお椀を作って、木がなくなったら、小屋を捨てて移動して、また別の土地で小屋を建ててっていうことを繰り返していく。
でも映画を撮った1970年代にはそういう木地師はもういなかったので、それを完全再現したんです。50年前に木地師の暮らしを経験していた人たちがいて、その人たちに記憶のまま再現してもらえたおかげで、2025年の今からすれば約100年前の映像を見てるのと同じことなんですよ。
DVDのレンタルについて
――今でも映画の制作は続けられているのですか?
箒さん 民映研としては制作していませんが、卒業していったディレクターたちが今でもいっぱい作ってます。民映研で仕事して、宮本常一先生のことも敬愛してっていう人たちですので、もう未来はそれで充分じゃないかなと。なのでうちはDVDをレンタルするだけにしているんですけど、毎月、日本のどこか10ヶ所ぐらいで自主的な上映会が開催されていますよ。
――シリーズで約120本もあるなんてすごく見応えありますよね。何年かかるかわからないですけど、全部見てみたいとか、DVDを個人で借りる方もいらっしゃるんですか?
箒さん いらっしゃいますよ。個人でも試写イベントで100人で見るのでも、レンタル料は一緒です。できるだけ多くの人が見てくれるのがありがたいです。
――配信はしないのですか?
箒さん 配信は簡単ですけど、理由があってレターパックでやってきました。それは一度もお会いしたことはないんですけど、毎月のように借りてくれる人が、返却のときに「相変わらずおもしろい」って手紙とか地元の野菜とかを入れてくれて。なのでこちらも次に送るときに作品についてのメモを添えたりします。そういうやり取りが始まると関係性も深まるじゃないですか。配信だとなかなかそうはいかない。
――確かにそうです。
箒さん 暮らしというのは関係性のことですから、民映研として「他者といかに関わるかというのが暮らしじゃないですか」ということを一生懸命記録してるのに、自分たちの作品を見せるときは「配信で」っておかしいですよね。まぁ、いつか配信ももっと人間的になる日が来るのかもしれないけど、現状はまだまだだと思ってます。
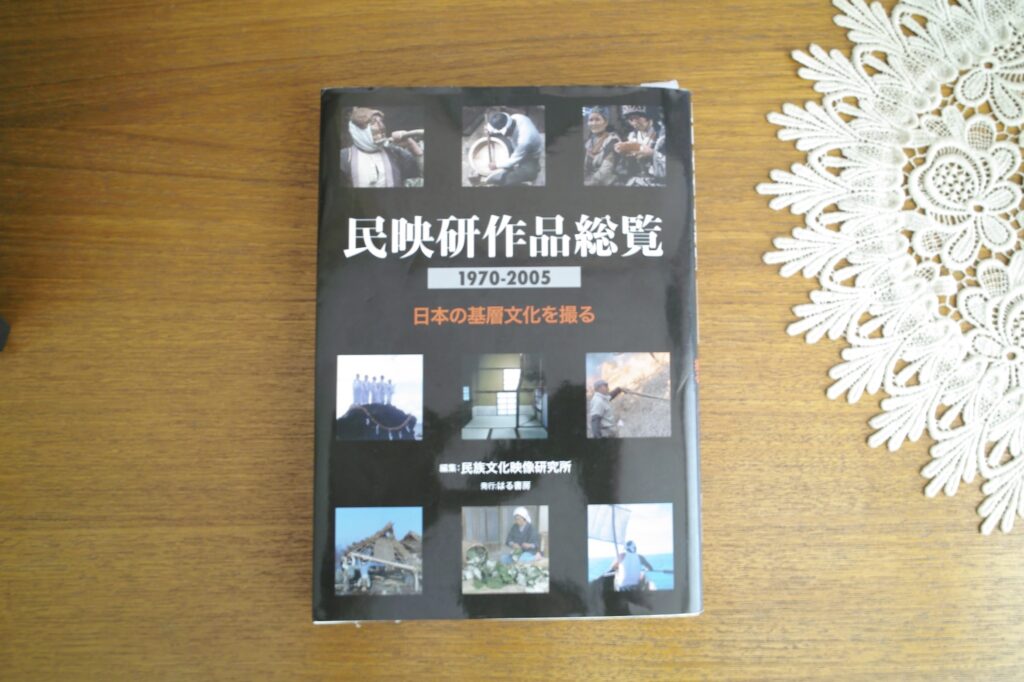
『民映研作品総覧』
口伝でなければ伝えられないこと
箒さん 『越後奥三面』という映画では熊狩りに行くシーンがあります。カメラマンも山の中を延々歩いてって、さあいよいよ熊を獲るというところはさすがに連れていってもらえないんですけど、その時の彼らの使う言葉では、山の中のすべてに名前がついてるんですよ。あのコブを越えて、クラを越えて、あそこ行って、ここで分かれるとか、その1つ1つのポイントに名前がついてるから、言葉だけで全員がイメージできる。
――頭の中の地図みたいなものですか?
箒さん そう。「どこどこにカモシカがいたよ」「そうなの」「あんなとこにいるの」っていうのがしっかりわかる。そういうのは、やっぱり年寄りから連綿と伝わる作業なので、大体高校生ぐらいから狩りについていって、そこで教わる。
――その社会で生きていくために身につけておかなきゃいけないことなんですよね。
箒さん 山の人たちは山の人たちの知識とルールがあるので、もしも登山者が遭難したりすると、土地の山男や猟師たちが入ってくる。彼らにとっては、全部に名前がついてるから意思の疎通がしっかりできるわけです。探すところも、「どこどこはもう探した」「どこどこで遭難したらしいぜ」「だったらこっちには絶対行かない」「あっちだけ探せばいい」っていうと、必ずそこに居るっていう。こういうスキルは高齢者から連綿と伝わってきたものですね。
――力強いです。
箒さん 紙に書いて勉強して教わるものではなく口伝なんですが、年長者から伝えられるという意味では、日本列島じゃなくても、地球上どこでもそうだと思いますけど、口から口へ伝わって覚えていくっていうのが最も大切かもしれないです。だからどうしても人と関わらないと生きていけないっていうのが「暮らし」ですよね。今は人と関わらないで暮らそうっていう努力をしっかりみんなしてるわけで。
伝統という「関わり」の重み
箒さん 例えばネットショッピングはポチっとしたら次の日に届いて利便だけど、そこに「関わり」はほぼないですよね。誰が作って、どうやって染めたの? とか、そんな会話のやり取りはない。そこはもう大きな穴ですよ。でもこれ、ウェブサイトで掲載される記事としてはまずいこと言っているかな?
――いや、続けてください。
箒さん 漆塗で言うと、最初に漆の木から漆を取る作業に使う特殊な刃物があるんです。これを作る鍛冶屋がいなくなると、漆掻きができなくなる。漆掻きをしないと、漆の材料がなくなり、漆の材料がないと漆を塗る人が困る。木地師は塗り物がなければ椀が作れない。最初の鍛冶屋がいなくなったら全部が廃業するわけですね。
――はい。
箒さん だから「伝統」という言葉には様々な階層の様々な職種が重なってる。本当はものすごい階層であらゆる職種が入り込んだ中で、最後にある形になって、それらを集約して言うときの言葉としての伝統というのが本当なのに、なぜか簡単に伝統という表現を使う人はこの世界観を一致させる努力の方を言わないんですよね。
――ちゃんと言葉を尽くして。
箒さん そう。言葉を尽くして。伝統を守るためにはこれこれ大変なんです。うちは伝統を活かした道具、これを作り、これを買ってもらうことによって、伝統を維持している様々な人たちに、分配していく――っていうような話ですよね。
――今日はのっけからお門違いなことを言ってしまいましたが、ひっくり返してくださってありがたかったです。とっても実のある話でした。上映会、やりたいです。
箒さん はい。ぜひ、やりましょう。
【民族文化映像研究所】
1976年に姫田忠義、伊藤碩男、小泉修吉の3人によって設立。民俗学者である宮本常一の教えを継ぎ、日本列島各地に残る基層文化を映像作品化。上映会は日本各地で行われているほか、映画祭で上映されることも。最新情報はFacebook「民映研」で随時告知しています。レンタルDVDは1本¥8,800~。
*レンタルDVDについてのお問い合わせ先:ho-ki@ohl-r.com